【なか食セレクション】伝統の「ご当地寿司」をお取り寄せ!ます寿司、柿の葉ずし、ままかり寿司などなど!
お寿司と言うと、江戸前の握り寿司を思い浮かべる方も多いかもしれません。
江戸前の握り、私も大好きです!


しかし、お寿司はニッポンの文化!
ずっと昔から伝わる、ご当地自慢のすばらしいお寿司も、全国各地にたくさんあります!
そんな「ご当地寿司」をご用意しました!ご旅行気分で、お楽しみください!
☆ます寿司(富山)
「ます寿司」は、薄紅色のサクラマスと酢飯を合わせて、若葉で包んだお寿司。若葉を開くと、若葉のかおりが、マスと酢飯に行き渡り、食欲をそそります。
☆柿の葉ずし(奈良)
「柿の葉ずし」は、鯖などの薄切りを酢飯にのせ、柿の葉でくるんだ押し寿司。江戸時代、奈良まで運ばれた塩漬けの魚をご飯と一緒に食べるために、殺菌効果の高い「柿の葉」で包んだことが始まりだそうです。柿の葉が、香りほのかで、魚の臭みも抜いてくれるので、とても食べやすいお寿司です。


☆手こね寿司(三重)
「手こね寿司」は、カツオやマグロなど、赤身の刺身を醤油ベースのタレに漬け込み、少し甘みのある酢飯と合わせたお寿司。薬味に、しょうが、のりなどを散らします。昔、漁師が船上で、ぶつ切りのかつおと、持って来た酢飯を「手でこねて」食べたのが、そのはじまりと言われています。
☆さんま寿司(和歌山)
「さんま寿司」は、開いたさんまを軽く塩漬けにしてから、お酢でしめ、木型に詰めた酢飯に乗せた押し寿司。志摩半島、熊野灘沿岸などで、祝い事やお祭りなどに作られる郷土料理です。
☆さば寿司(福井~京都)
福井の若狭湾から京都まで。日本海で水揚げされた「鯖」に塩をふり、それを運んだ道「鯖街道」。その始まりは、平安時代、奈良時代までさかのぼります。「さば寿司」は鯖街道とともに、まさに、ニッポンの文化、伝統です!
☆ままかり寿司(岡山)
「ままかり寿司」は、サッパと呼ばれるニシン科の小魚を二枚におろし、塩をふって、酢に漬け込んだお寿司。なぜ「サッパ」ではなく「ままかり」なのか?それは、その味があまりにおいしく、お隣から「まま(ご飯)」を借りてくるほどだったことから「ままかり」の名前になったそうです。
※「うまログ!」は、木村進の食べ歩きのブログサイトです。
※サイトは毎週更新。新着情報は Twitter(X) でお知らせしています。
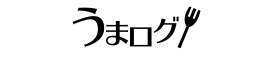







“【なか食セレクション】伝統の「ご当地寿司」をお取り寄せ!ます寿司、柿の葉ずし、ままかり寿司などなど!” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。